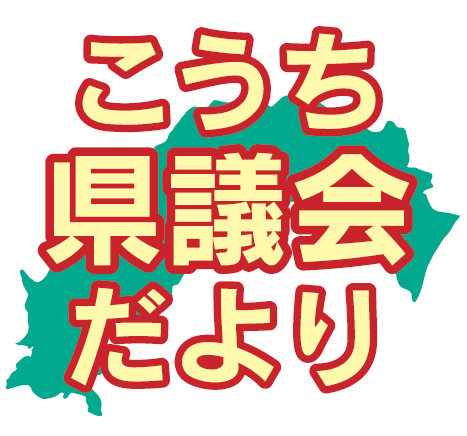
土佐龍馬であい博開催中! 11月定例会トピックス 11月定例会本会議の質問から 11月定例会審議の結果 常任委員会の動き(11月~1月) 特別委員会の動き(12月~2月) 11月定例会常任委員会委員長報告要旨 お知らせ
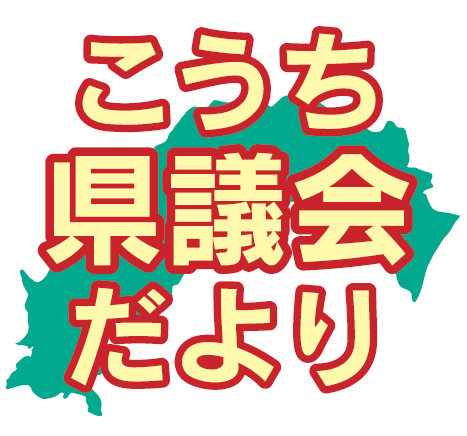 |
第44号 もくじ 土佐龍馬であい博開催中! 11月定例会トピックス 11月定例会本会議の質問から 11月定例会審議の結果 常任委員会の動き(11月~1月) 特別委員会の動き(12月~2月) 11月定例会常任委員会委員長報告要旨 お知らせ |
11月定例会本会議の質問から |
|
| 12月4日 |
児童虐待問題への取組について聞く! |
問 児童虐待問題に対する各
機関の連携した取組への所見
を聞く。 答 地域福祉部長 昨年度から 市町村職員も含め、児童福祉司 の養成研修を実施し、専門職の 育成確保に取り組むとともに、 市町村での児童虐待対応のマニ ュアルを改訂して、実務の手引 書として活用されるよう取り組 んでいる。また、市町村の要保 護児童対策地域協議会に対し、 児童相談所の職員がアドバイス をする等の支援を行い、対応力 の強化に努めている。今後も、 同協議会を中心に、関係機関の 連携と相談体制の充実強化を図 り、迅速かつ的確に対応できる よう取り組む。 問 地方の公共交通体系を 維持していくことに積極的に関 与し、具体的な支援をすべきだ。 現状と課題についての所見を聞く。 答 交通運輸政策担当理事 利 用者の減少等 |
に加え、昨年から
は景気低迷や高速道路料金の割
引等の要因が交通事業者の経営
を一層圧迫している。近年、乗
合タクシーの運行やデマンド式
運行等が行われ始めているが、
市町村負担の増大の問題がある。
地方だけで地域の交通を支える
ことは困難なので、国の支援の
充実に向け、地方の実態を国に
十分伝えていく。 問 国の事業仕分けでシルバ ー人材センターへの補助金が 3分の1カットされたが、セ ンターが存続できるように格 段の支援策を望む。 答 商工労働部長 意欲のある 高齢者が、地域に密着した多様 な就業を通じ、社会参加をして いくことは、高齢化が先行して いる本県、また人手が不足しが ちな地域にとっても大切なこと だ。国の来年度予算の編成の動 向を注視するとともに、市町村 とも連携しながら、地域のセン ターが存続し、活動に必要な予 算が確保されるよう努める。 |
赤バイの配備状況と利活用を聞く! |
問 緊急消防自動二輪車(赤
バイ)の県下での配備状況と
今後の利活用について聞く。 答 危機管理部長 4消防団で 18台保有し、このうち高知市と いの町では赤バイ隊を設置して いる。このほか安芸市消防団で は、団員が所有するオフロード バイク5台でのバイク隊を3月 に設置した。大規模災害の場合、 機動性の高い二輪車は、災害対 策を迅速に進める上で有効だ。 一方、安全確保や運転技量を持 った団員の育成等の課題もある。 配備、活用は、各自治体が判断 することになるが、県は、消防 関係機関との協議の場等で、有 効性や実績等の情報を提供する。 問 桂浜への大渋滞の緩和や 観光の一つの方法として、高 知新港から船で桂浜に行く方 法を提案する。 答 観光振興部長 御提案の方 法は、海上保安部や運輸局との 綿密な事前協議が必要で、 |
浮き
桟橋等の機材整備、他の岸壁利
用者との調整等の課題もあるが、
浦戸湾や桂浜を海から巡るコー
スの充実は、新たな観光資源と
して魅力的だ。渋滞緩和の一助
にもつながるので、航路や港湾
の管理者、岸壁利用者、高知市
観光遊覧船を運航するNPO法
人等の関係者と検討する。 問 高知市介良地区で、再生 稲や二期作で発酵粗飼料用の 稲をつくる取組がされているが、 これを進めていく考えはないか。 また、進めていくに当たっての 課題はないか。 答 農業振興部長 産業振興計 画にも位置付け、本年度は収穫 機械等の導入も支援した。介良 地区では平成19年度に0.1ヘ クタールから始めた生産が今年 度は約19ヘクタール、県下で約 34ヘクタールでの生産となった。 今後は畜産農家の需要に応じた 増産が大きな課題だ。県下各地 で需給調整できるよう耕畜連携 の体制づくりを進める。 |
太陽光発電と電気自動車を活用した県づくりを! |
問 県が主導的に太陽光発電
と電気自動車を活用した県づ
くりに取り組む考えはないか。 答 知事 太陽光発電と電気自 動車は、新ビジネスの可能性を 秘めている。県内にも関連事業 を進めようとする企業があり、 本年度設置した研究会に参加い ただいている。研究会の活動を 通じ、最新情報の収集や技術開 発を行う等の活用を望んでいる。 太陽光発電や電気自動車を活用 する取組は、新たな産業づくり にとどまらず、全国トップクラ スの日照時間で、低炭素社会づ くりを目指す本県にとって大切 にしなければならない視点だ。 問 中山間地域の活性化策の 一つとして注目を集めている 庭先集荷のシステムを、高知 県で確立するとともに、国に 制度化を要望すべきではないか。 答 知事 本県のように高齢者 の多い中山間地域の活性化等の ために大事な取組なので、支 |
援
策を考えていく。今後は中山間
地域の人、物のすべての動きを
支えるという視点で、庭先集荷
に加えて、スクールバスなど、さ
まざまなニーズにまとめて対応
できる多機能型の仕組みの検討
を進めていく。国にも、制度支
援の必要性を積極的に提案する。 問 県は、一本釣りカツオ産 業の振興にどう取り組んでい くのか。 答 水産振興部長 「海のエコ ラベル」等の取得は、エコに関 心の高い消費者の支持も期待さ れるので、多くの漁船で取得で きるよう一本釣り漁業関係者と 協議する。地元への水揚げの拡 大については、えさとなるイワ シの供給拠点づくりを産業振興 計画にも位置付けて取り組んで きた。黒潮町佐賀地区では漁港 内の施設整備の支援等を行う。 イワシ供給事業が定着すると、 水揚げの増加など、地域への経 済効果も大きいのではないかと 期待している。 |