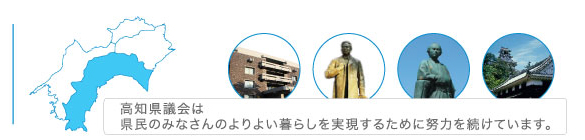平成22年12月定例会の概要(12月7日(火) - 12月22日(水) 会期:16日間)
公開日 2022年07月27日
INDEX
日程
定例会日程
12月7日(火) - 12月22日(水) (会期:16日間)
| 月 | 日 | 曜 | 会議 | 行事 | 中継 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 火 | 本会議 | 開会、議案上程、知事説明ほか | |
| 8 | 水 | 休会 | 議案精査 | ||
| 9 | 木 | 〃 | 〃 | ||
| 10 | 金 | 本会議 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者◇ 浜田英宏(自由民主党) 式地寛肇(県政会) 田村輝雄(民主党・県民クラブ) |
||
| 11 | 土 | 休会 | 休日 | ||
| 12 | 日 | 〃 | 〃 | ||
| 13 | 月 | 〃 | 議事整理日 | ||
| 14 | 火 | 本会議 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者◇ 塚地佐智(日本共産党と緑心会) ふぁーまー土居(南風(みなみかぜ)) 佐竹紀夫(自由民主党) |
||
| 15 | 水 | 〃 | 質疑並びに一般質問 ◇質問者◇ 梶原大介(県政会) 山本広明(自由民主党) |
||
| 16 | 木 | 休会 | 常任委員会 | ||
| 17 | 金 | 〃 | 〃 | ||
| 18 | 土 | 休会 | 休日 | ||
| 19 | 日 | 〃 | 〃 | ||
| 20 | 月 | 〃 | 常任委員会 | ||
| 21 | 火 | 〃 | 議事整理日 | ||
| 22 | 水 | 本会議 | 委員長報告、採決、閉会 |
議決結果一覧
1. 議案関係
| 事件の番号 | 件名 | 議決結果 | 議決年月日 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 平成22年度高知県一般会計補正予算 | 原案可決 | H22.12.22 |
| 第2号 | 平成22年度高知県給与等集中管理特別会計補正予算 | 〃 | 〃 |
| 第3号 | 平成22年度高知県用品等調達特別会計補正予算 | 〃 | 〃 |
| 第4号 | 平成22年度高知県流域下水道事業特別会計補正予算 | 〃 | 〃 |
| 第5号 | 平成22年度高知県電気事業会計補正予算 | 〃 | 〃 |
| 第6号 | 平成22年度高知県工業用水道事業会計補正予算 | 〃 | 〃 |
| 第7号 | 平成22年度高知県病院事業会計補正予算 | 〃 | 〃 |
| 第8号 | 高知県ワクチン接種緊急促進基金条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第9号 | 高知県公立大学法人への職員の引継ぎに関する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第10号 | 高知県立地域職業訓練センターの設置及び管理に関する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第11号 | 県立大学の公立大学法人化に伴う関係条例の整備に関する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第12号 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第13号 | 高知県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第14号 | 高知県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第15号 | 高知県防災会議条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第16号 | 高知県消防法関係手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第17号 | 県立大学の設置及び管理に関する条例を廃止する条例議案 | 〃 | 〃 |
| 第18号 | 平成23年度当せん金付証票の発売総額に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第19号 | 中土佐町と四万十町との境界の一部を変更する議案 | 〃 | 〃 |
| 第20号 | 高知県公立大学法人定款に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第21号 | 高知県立ふくし交流プラザの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第22号 | 高知県立障害者スポーツセンターの指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第23号 | 高知県立牧野植物園の指定管理者の指定に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第24号 | 県有財産(高知岡豊工業団地)の処分に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第25号 | 高知県公立大学法人に承継させる権利に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第26号 | 県が行う土地改良事業に対する市町村の負担の一部変更に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第27号 | 国道441号地域活力基盤創造交付金(川登トンネル)工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第28号 | 県道高知南インター線地域活力基盤創造交付金(五台山トンネル)工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第29号 | 県道高知南インター線道路改築(坂本橋上部工)工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第30号 | 安芸総合庁舎建替建築主体工事請負契約の締結に関する議案 | 〃 | 〃 |
| 第31号 | 高知県教育委員会の委員の任命についての同意議案 | 同意 | 〃 |
| 第32号 | 高知県土地利用審査会の委員の任命についての同意議案 | 〃 | 〃 |
| 第33号 | 高知県収用委員会の委員の任命についての同意議案 | 〃 | 〃 |
| 308 報第1号 |
平成21年度高知県一般会計歳入歳出決算 | 認定 | H22.12.7 |
| 308 報第2号 |
平成21年度高知県給与等集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第3号 |
平成21年度高知県旅費集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第4号 |
平成21年度高知県用品等調達特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第5号 |
平成21年度高知県会計事務集中管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第6号 |
平成21年度高知県県債管理特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第7号 |
平成21年度高知県土地取得事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第8号 |
平成21年度高知県災害救助基金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第9号 |
平成21年度高知県母子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第10号 |
平成21年度高知県中小企業近代化資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第11号 |
平成21年度高知県流通団地及び工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第12号 |
平成21年度高知県農業改良資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第13号 |
平成21年度高知県県営林事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第14号 |
平成21年度高知県林業・木材産業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第15号 |
平成21年度高知県沿岸漁業改善資金助成事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第16号 |
平成21年度高知県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第17号 |
平成21年度高知県港湾整備事業特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第18号 |
平成21年度高知県高等学校等奨学金特別会計歳入歳出決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第19号 |
平成21年度高知県電気事業会計決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第20号 |
平成21年度高知県工業用水道事業会計決算 | 〃 | 〃 |
| 308 報第21号 |
平成21年度高知県病院事業会計決算 | 〃 | 〃 |
| 議発 第1号 |
ロシア大統領の北方領土訪問に対し、毅然とした外交姿勢を求める意見書議案 | 原案可決 | H22.12.22 |
| 議発 第2号 |
受診抑制を拡大する70歳から74歳の窓口負担1割の引き上げに反対する意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第3号 |
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)総合対策を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第4号 |
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第5号 |
米価大暴落に歯どめをかけるための意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第6号 |
燃油減免制度の継続を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第7号 |
保育制度改革に関する意見書議案 | 否決 | 〃 |
| 議発 第8号 |
国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第9号 |
公費負担拡大で介護保険制度の改善を求める意見書議案 | 〃 | 〃 |
| 議発 第10号 |
議会の機能強化及び地方議会議員の法的位置づけの明確化等を求める意見書議案 | 原案可決 | 〃 |
2請願関係
北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であることは明白であり、ロシアも1993年の「東京宣言」において「北方四島の帰属に関する問題については、歴史的・法的事実に立脚し、両国間での合意の上、作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決する」との指針を確認している。
旧ソ連時代を含め、ロシアの国家元首が北方領土を訪問したのは初めてであり、大統領の訪問はこうした日ロ両国間の合意を無視し、ロシアによる四島の不法占拠を既成事実化しようとするものである。
よって、国におかれては、今般のメドベージェフ大統領の北方領土訪問に厳重に抗議するとともに、毅然たる外交姿勢でロシアに対して臨むよう強く求めるとともに、北方領土問題を早期解決に導くためにも、早急に外交戦略の立て直しを図るよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣
国家戦略担当大臣様
その中で、高齢者の保険料を9割軽減する措置の段階的縮小を新たに打ち出し、70~74歳の患者負担を、2013年度に70歳に到達した人から順次、医療費の1割を2割に引き上げる内容を示した。
国民年金は満額でも月6万6千円にしかならず、低所得の高齢者の暮らしはとりわけ厳しいものがあり、これ以上の負担増には耐えられないのは明白である。
第4回高齢者医療制度改革会議に提出された、65歳以上の高齢者の所得と受診の関連について行われた調査資料では、所得が低いほど、過去1年間に治療を控えたことがあると回答しており、年齢の違いを考慮しても、高所得者の9.3%に対し、低所得者では13.3%が受診を控えているとの結果が示されている。また、低所得者ほど、その理由として「費用」を挙げる割合が高くなっており、高所得者10.6%に対し、低所得者は32.8%となっている。現在の自己負担でも、高齢者層に受診抑制が起きていることが明らかとなっている。病状の悪化をもたらす受診抑制に歯止めをかけるため、窓口負担の軽減は急務であるにもかかわらず、世界的に見て異常に高い、高齢者の窓口負担を現状より引き上げることは容認できるものではない。
よって、国におかれては、2011年度以降も1割負担を引き上げないこと、低所得者の保険料軽減措置の維持を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣様
現在の主な感染経路は、母乳を介して母親から子供に感染する母子感染と性交渉による感染であり、そのうち母子感染が6割以上を占めている。このウイルスの特徴は、感染から発症までの潜伏期間が40年から60年と期間が長いことである。そのため、自分自身がキャリアであると知らずに子供を母乳で育て、数年後に自身が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがある。この場合、母親の苦悩は言葉では言いあらわせない。一部自治体では、妊婦健康診査時にHTLV-1抗体検査を実施し、陽性の妊婦には授乳指導を行うことで、効果的に感染の拡大を防止している。
平成22年10月6日、厚生労働省は、官邸に設置された「HTLV-1特命チーム」における決定を受け、HTLV-1抗体検査を妊婦健康診査の標準的な検査項目に追加し、妊婦健康診査臨時特例交付金に基づく公費負担の対象とできるよう、通知を改正し、各自治体に発出した。これにより全国で感染拡大防止対策が実施されることになる。そのためには、医療関係者のカウンセリング研修やキャリア妊婦等の相談体制の充実を図るとともに、診療拠点病院の整備、予防・治療法の研究開発、国民への正しい知識の普及啓発等の総合的な対策の推進が不可欠である。
よって、国におかれては、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)の感染拡大防止に伴う「HTLV-1総合対策」を推進するため、次の項目について早急に実現するよう強く要望する。
1医療関係者や地域保健担当者を対象とした研修会を早急に実施すること。
2検査体制、保健指導・カウンセリング体制の整備を図ること。
3感染者および発症者の相談支援体制の充実を図ること。
4感染者および発症者のための診療拠点病院の整備を推進すること。
5発症予防や治療法に関する研究開発を大幅に推進すること。
6国民に対する正しい知識の普及と理解の促進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
内閣総理大臣
厚生労働大臣様
ことし4月、厚生労働省より、本症とわかる前の検査費用は保険適用との事務連絡が出された。これは、本来、検査費用は保険適用であるはずのものが、地域によって対応が異なっていたため、それを是正するため出されたもので、患者にとり朗報であった。しかし、本症の治療に有効であるブラッドパッチ療法については、いまだ保険適用されず、高額な医療費負担に、患者及びその家族は、依然として厳しい環境におかれている。
平成19年度から開始された「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業(当初3年間)は、症例数において中間目標100症例達成のため、本年度も事業を継続して行い、本年8月についに、中間目標数を達成した。今後は、収集した症例から基礎データをまとめ、診断基準を示すための作業を速やかに行い、本年度中に診断基準を定めるべきである。そして、来年度には、診療指針(ガイドライン)の策定及びブラッドパッチ療法の治療法としての確立を図り、早期に保険適用とすべきである。また、本症の治療に用いられるブラッドパッチ療法を、学校災害共済、労災、自賠責保険等の対象とすべきである。
よって、国におかれては、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するよう、次の項目を強く求める。
1「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、症例数において中間目標(100症例)が達成されたため、早急に脳脊髄液減少症の診断基準を定めること。
2「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、早急に、ブラッドパッチ治療を含めた診療指針(ガイドライン)を策定し、ブラッドパッチ療法(自家血硬膜外注入)を脳脊髄液減少症の治療法として確立し、早期に保険適用とすること。
3脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険の対象に、速やかに加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣様
各地のJAが示した概算金は1万円程度、中には七千円台という驚くべき水準で、農家に衝撃を与えている。今農村では、農家が余りにも安い米価に失望し、無策で冷淡な政府の姿勢に憤りを募らせている。こうした事態を生み出した最大の原因は、戸別所得補償を口実に「価格対策はとらない」と公言してきた政府の姿勢にあることは明らかである。
この数年来、生産費を大幅に下回る米価が続いている中で、生産者の努力は限界を超えており、かつて経験したことのない米価の下落が、日本農業の大黒柱である稲作存続の土台を破壊し、それはまた国民への主食の安定供給を困難にするものと考える。
米の需給を引き締めて価格を安定・回復させるためには、政府が年産にかかわらず、過剰米を40万トン程度、緊急に買い入れることが最も効果的であると考える。
よって、国におかれては、米価下落対策として、直ちに40万トン程度の買い入れを行うよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
内閣総理大臣
農林水産大臣様
また、現在、政府が昨年一年間延長したA重油の免税・還付措置も廃止される状況にある。
免税軽油とは、特段の政策的配慮の観点から、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税するという制度であって、農業用の機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)や船舶などに使用する軽油について、申請することにより認められてきた。
軽油、A重油の減免措置がなくなれば、今でさえ困難な農漁業経営への影響は避けられず、軽油、A重油を大量に使う畜産農家や野菜・園芸農家を初め、本県産業の中心である農漁業経営への影響は深刻である。制度の継続は、地域農漁業の振興、食料自給率を向上させる観点からも有効であり、その継続が強く望まれている。
よって、国におかれては、免税軽油の制度の継続と、A重油の免税・還付措置を継続するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣様
地方議会は、これまで議会活動の透明性の向上を図りながら、議会に与えられた機能を充実するため自己改革に努めてきた。今後とも地方議会は、住民の負託と信頼にこたえるため、地域の実情に即した自主的な議会運営を目指すとともに、住民に対する説明責任を自覚し、みずから議会機能の向上に努めなければならない。その上で、地方分権をさらに推し進めるためには、議会活動の自由度を高めつつ、地方政府における立法府にふさわしい法的権限を確立する必要がある。
また、議会を構成する地方議会議員が、本会議・委員会において行政に対する監視や政策立案のための充実した審議を行うことは、当該地方自治体の事務に関する調査研究や、住民意思の把握など不断の議員活動に支えられている。しかしながら、議員の責務に関する法律上の規定がないこともあり、議員活動に対する住民の理解が十分得られていないのが現状である。議会が住民に期待される機能を十分発揮できるようにするため、公選職としての地方議会議員の責務を法律上明記するとともに、専業化している都道府県議会議員の特性を踏まえて、議員の責務を果たすにふさわしい活動基盤を強化することが喫緊の課題となっている。
さらに、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすることにより、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の振興を図る制度とすることも重要な課題である。
よって、国におかれては、速やかに関係法律の改正を行い、地方政府における立法府にふさわしい地方議会の法的権限を確立するとともに、選挙制度の見直しを含め地方議会議員の活動基盤を強化するため、次の事項を実現するよう強く要請する。
1地方自治法の抜本改正に当たっては、議会の権限を明確にするため、議会の立法権及び行政監視権を明示する基本規定を設けるとともに、会期制度のあり方など議会の活動・運営・組織に関する事項は条例及び会議規則にゆだねること。
なお、専決処分や再議など長優位の制度は抜本的に見直すこと。
2真の二元代表制を実現するため、議長に議会の招集権を付与すること。
3議会意思を確実に国政等に反映させるため、議会が議決した意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務づけること。
4住民から選挙で選ばれる「公選職」としての地方議会議員の特性を踏まえ、その責務を法律上明らかにするとともに、責務遂行の対価について、都道府県議会議員については「地方歳費」または「議員年俸」とすること。
5地方議会議員の活動基盤を強化するため、現在法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直し、住民意思の把握や議員活動報告のための諸活動を加え、幅広い議員活動または会派活動に充てることができることを明確にすること。
6住民意思を正しく議会意思に反映させるとともに地域の振興を図るため、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
国家戦略担当大臣
内閣官房長官様
| 事件の 番号 |
件名 | 議決結果 | 議決 年月日 |
| 請 第2号 |
公共工事における賃金確保法(公契約法)の条例制定など建設労働者の安定した賃金確保の基準づくりについて | 取下げ承認 | H22.12.22 |
| 請 第3-1号 |
すべての子供に行き届いた教育を進めるための請願について | 不採択 | 〃 |
| 請 第3-2号 |
すべての子供に行き届いた教育を進めるための請願について | 〃 | 〃 |
| 請 第4号 |
教育費負担の公私間格差をなくし、子供たちに行き届いた教育を求める私学助成の請願について | 〃 | 〃 |
意見書
可決された意見書
ロシア大統領の北方領土訪問に対し、毅然とした外交姿勢を求める意見書
ロシアのメドベージェフ大統領が11月1日国後島へ、続く12月13日にはシュワロフロシア第一副首相が、国後島・択捉島を訪問した。北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であることは明白であり、ロシアも1993年の「東京宣言」において「北方四島の帰属に関する問題については、歴史的・法的事実に立脚し、両国間での合意の上、作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決する」との指針を確認している。
旧ソ連時代を含め、ロシアの国家元首が北方領土を訪問したのは初めてであり、大統領の訪問はこうした日ロ両国間の合意を無視し、ロシアによる四島の不法占拠を既成事実化しようとするものである。
よって、国におかれては、今般のメドベージェフ大統領の北方領土訪問に厳重に抗議するとともに、毅然たる外交姿勢でロシアに対して臨むよう強く求めるとともに、北方領土問題を早期解決に導くためにも、早急に外交戦略の立て直しを図るよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣
国家戦略担当大臣様
受診抑制を拡大する70歳から74歳の窓口負担1割の引き上げに反対する意見書
厚生労働省は12月8日、後期高齢者医療制度にかわる「新制度」を議論している高齢者医療制度改革会議に最終案を示した。その中で、高齢者の保険料を9割軽減する措置の段階的縮小を新たに打ち出し、70~74歳の患者負担を、2013年度に70歳に到達した人から順次、医療費の1割を2割に引き上げる内容を示した。
国民年金は満額でも月6万6千円にしかならず、低所得の高齢者の暮らしはとりわけ厳しいものがあり、これ以上の負担増には耐えられないのは明白である。
第4回高齢者医療制度改革会議に提出された、65歳以上の高齢者の所得と受診の関連について行われた調査資料では、所得が低いほど、過去1年間に治療を控えたことがあると回答しており、年齢の違いを考慮しても、高所得者の9.3%に対し、低所得者では13.3%が受診を控えているとの結果が示されている。また、低所得者ほど、その理由として「費用」を挙げる割合が高くなっており、高所得者10.6%に対し、低所得者は32.8%となっている。現在の自己負担でも、高齢者層に受診抑制が起きていることが明らかとなっている。病状の悪化をもたらす受診抑制に歯止めをかけるため、窓口負担の軽減は急務であるにもかかわらず、世界的に見て異常に高い、高齢者の窓口負担を現状より引き上げることは容認できるものではない。
よって、国におかれては、2011年度以降も1割負担を引き上げないこと、低所得者の保険料軽減措置の維持を強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣様
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)総合対策を求める意見書
ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)は、致死率の高い「成人T細胞白血病(ATL)」や、進行性の歩行・排尿障害を伴う「せき髄疾患(HAM)」等を引き起こす。国内の感染者数(キャリア)は100万人以上と推定され、その数はB型・C型肝炎に匹敵する。毎年約1,000人以上がATLで命を落とし、HAM発症者は激痛や両足麻痺、排尿障害に苦しんでいる。一度感染すると現代の医学ではウイルスを排除することができず、いまだに根本的な治療法は確立されていない。現在の主な感染経路は、母乳を介して母親から子供に感染する母子感染と性交渉による感染であり、そのうち母子感染が6割以上を占めている。このウイルスの特徴は、感染から発症までの潜伏期間が40年から60年と期間が長いことである。そのため、自分自身がキャリアであると知らずに子供を母乳で育て、数年後に自身が発症して初めて我が子に感染させてしまったことを知らされるケースがある。この場合、母親の苦悩は言葉では言いあらわせない。一部自治体では、妊婦健康診査時にHTLV-1抗体検査を実施し、陽性の妊婦には授乳指導を行うことで、効果的に感染の拡大を防止している。
平成22年10月6日、厚生労働省は、官邸に設置された「HTLV-1特命チーム」における決定を受け、HTLV-1抗体検査を妊婦健康診査の標準的な検査項目に追加し、妊婦健康診査臨時特例交付金に基づく公費負担の対象とできるよう、通知を改正し、各自治体に発出した。これにより全国で感染拡大防止対策が実施されることになる。そのためには、医療関係者のカウンセリング研修やキャリア妊婦等の相談体制の充実を図るとともに、診療拠点病院の整備、予防・治療法の研究開発、国民への正しい知識の普及啓発等の総合的な対策の推進が不可欠である。
よって、国におかれては、ヒトT細胞白血病ウイルス1型(HTLV-1)の感染拡大防止に伴う「HTLV-1総合対策」を推進するため、次の項目について早急に実現するよう強く要望する。
1医療関係者や地域保健担当者を対象とした研修会を早急に実施すること。
2検査体制、保健指導・カウンセリング体制の整備を図ること。
3感染者および発症者の相談支援体制の充実を図ること。
4感染者および発症者のための診療拠点病院の整備を推進すること。
5発症予防や治療法に関する研究開発を大幅に推進すること。
6国民に対する正しい知識の普及と理解の促進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
内閣総理大臣
厚生労働大臣様
脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書
脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等の身体への強い衝撃が原因で、脳脊髄液が漏れ、減少することによって引き起こされ、頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感等、多種多様な症状が複合的にあらわれるという特徴をもっている。ことし4月、厚生労働省より、本症とわかる前の検査費用は保険適用との事務連絡が出された。これは、本来、検査費用は保険適用であるはずのものが、地域によって対応が異なっていたため、それを是正するため出されたもので、患者にとり朗報であった。しかし、本症の治療に有効であるブラッドパッチ療法については、いまだ保険適用されず、高額な医療費負担に、患者及びその家族は、依然として厳しい環境におかれている。
平成19年度から開始された「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業(当初3年間)は、症例数において中間目標100症例達成のため、本年度も事業を継続して行い、本年8月についに、中間目標数を達成した。今後は、収集した症例から基礎データをまとめ、診断基準を示すための作業を速やかに行い、本年度中に診断基準を定めるべきである。そして、来年度には、診療指針(ガイドライン)の策定及びブラッドパッチ療法の治療法としての確立を図り、早期に保険適用とすべきである。また、本症の治療に用いられるブラッドパッチ療法を、学校災害共済、労災、自賠責保険等の対象とすべきである。
よって、国におかれては、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するよう、次の項目を強く求める。
1「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、症例数において中間目標(100症例)が達成されたため、早急に脳脊髄液減少症の診断基準を定めること。
2「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、早急に、ブラッドパッチ治療を含めた診療指針(ガイドライン)を策定し、ブラッドパッチ療法(自家血硬膜外注入)を脳脊髄液減少症の治療法として確立し、早期に保険適用とすること。
3脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険の対象に、速やかに加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣様
米価大暴落に歯どめをかけるための意見書
農林水産省は、米戸別所得補償モデル事業によって米の需給は均衡し米価は安定するとしてきたが、相対価格は下落を続け、22年産の9月の相対価格は前年を14%、2,000円も下回る事態に至っている。各地のJAが示した概算金は1万円程度、中には七千円台という驚くべき水準で、農家に衝撃を与えている。今農村では、農家が余りにも安い米価に失望し、無策で冷淡な政府の姿勢に憤りを募らせている。こうした事態を生み出した最大の原因は、戸別所得補償を口実に「価格対策はとらない」と公言してきた政府の姿勢にあることは明らかである。
この数年来、生産費を大幅に下回る米価が続いている中で、生産者の努力は限界を超えており、かつて経験したことのない米価の下落が、日本農業の大黒柱である稲作存続の土台を破壊し、それはまた国民への主食の安定供給を困難にするものと考える。
米の需給を引き締めて価格を安定・回復させるためには、政府が年産にかかわらず、過剰米を40万トン程度、緊急に買い入れることが最も効果的であると考える。
よって、国におかれては、米価下落対策として、直ちに40万トン程度の買い入れを行うよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
内閣総理大臣
農林水産大臣様
燃油減免制度の継続を求める意見書
これまで農漁家の経営に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正によって、このままでは2012年(平成24年)3月末で廃止される状況にある。また、現在、政府が昨年一年間延長したA重油の免税・還付措置も廃止される状況にある。
免税軽油とは、特段の政策的配慮の観点から、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税するという制度であって、農業用の機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械など)や船舶などに使用する軽油について、申請することにより認められてきた。
軽油、A重油の減免措置がなくなれば、今でさえ困難な農漁業経営への影響は避けられず、軽油、A重油を大量に使う畜産農家や野菜・園芸農家を初め、本県産業の中心である農漁業経営への影響は深刻である。制度の継続は、地域農漁業の振興、食料自給率を向上させる観点からも有効であり、その継続が強く望まれている。
よって、国におかれては、免税軽油の制度の継続と、A重油の免税・還付措置を継続するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣様
議会の機能強化及び地方議会議員の法的位置づけの明確化等を求める意見書
地方分権をさらに推進するためには、地方政府における自治立法権を担う地方議会が住民に対する説明責任を果たしながら、政策立案機能、監視機能を十分に発揮する必要がある。特に、義務づけ・枠づけの緩和などにより地方自治体の条例制定権が広がることに伴い、政策を提言し行政を監視する地方議会の役割と責任はますます大きなものとなる。地方議会は、これまで議会活動の透明性の向上を図りながら、議会に与えられた機能を充実するため自己改革に努めてきた。今後とも地方議会は、住民の負託と信頼にこたえるため、地域の実情に即した自主的な議会運営を目指すとともに、住民に対する説明責任を自覚し、みずから議会機能の向上に努めなければならない。その上で、地方分権をさらに推し進めるためには、議会活動の自由度を高めつつ、地方政府における立法府にふさわしい法的権限を確立する必要がある。
また、議会を構成する地方議会議員が、本会議・委員会において行政に対する監視や政策立案のための充実した審議を行うことは、当該地方自治体の事務に関する調査研究や、住民意思の把握など不断の議員活動に支えられている。しかしながら、議員の責務に関する法律上の規定がないこともあり、議員活動に対する住民の理解が十分得られていないのが現状である。議会が住民に期待される機能を十分発揮できるようにするため、公選職としての地方議会議員の責務を法律上明記するとともに、専業化している都道府県議会議員の特性を踏まえて、議員の責務を果たすにふさわしい活動基盤を強化することが喫緊の課題となっている。
さらに、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすることにより、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の振興を図る制度とすることも重要な課題である。
よって、国におかれては、速やかに関係法律の改正を行い、地方政府における立法府にふさわしい地方議会の法的権限を確立するとともに、選挙制度の見直しを含め地方議会議員の活動基盤を強化するため、次の事項を実現するよう強く要請する。
1地方自治法の抜本改正に当たっては、議会の権限を明確にするため、議会の立法権及び行政監視権を明示する基本規定を設けるとともに、会期制度のあり方など議会の活動・運営・組織に関する事項は条例及び会議規則にゆだねること。
なお、専決処分や再議など長優位の制度は抜本的に見直すこと。
2真の二元代表制を実現するため、議長に議会の招集権を付与すること。
3議会意思を確実に国政等に反映させるため、議会が議決した意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務づけること。
4住民から選挙で選ばれる「公選職」としての地方議会議員の特性を踏まえ、その責務を法律上明らかにするとともに、責務遂行の対価について、都道府県議会議員については「地方歳費」または「議員年俸」とすること。
5地方議会議員の活動基盤を強化するため、現在法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直し、住民意思の把握や議員活動報告のための諸活動を加え、幅広い議員活動または会派活動に充てることができることを明確にすること。
6住民意思を正しく議会意思に反映させるとともに地域の振興を図るため、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
高知県議会議長溝渕健夫
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
国家戦略担当大臣
内閣官房長官様